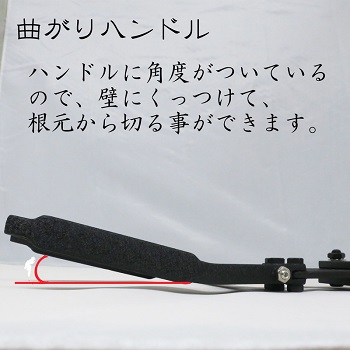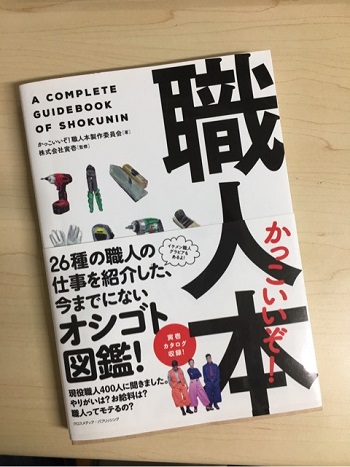S-tool1721ダブルソケット限定色!
S-toolさんからダブルソケット限定色のご案内です。
ソケットの中でもダントツ人気のS-toolさんのダブルソケット。
1721だけでも6角、12角、6角と12角、逆ソケと何種類もありますが、今回3種類が限定色として追加されました!
1721とも12角タイプはスライドとソケットの部分がゴールド。
1721とも6角タイプがスライドとソケットの部分がメタリックレッド。
17が6角21が12角のタイプはスライドがゴールドでソケットの部分がメタリックレッドと
サイズに合わせて分かりやすくなっているのかなっていないのか分かりませんが色別になっています。
しかもボディもガンメタ仕様で色の組み合わせが自然です。
限定色、数に限りがありますので、どうぞお早めに。
差替えビット1本ついてます。
~蕨~地名の由来1
当店がお世話になっておりますこの蕨市。
何気なく、この地で店を構えていましたが、なんだか調べてみると色々と面白そうです。
まず、
●面積が日本で一番小さな市。(町村を合わせても下から8番目!)
●人口密度が市町村で一番多い市。23区を合わせても全国で17位!)
●成人式発祥の地(蕨では成年式という)
●日本の市町村を50音順に並べると最後に来る
●JR路線で50音順で最後の駅。
(国内すべての駅だと割出駅(わりだしえき←北陸鉄道石川県)が最後(惜しい!)
軽く日本一が多くてびっくりです!
そんな蕨の地名はどこからきたのかしらべてみました。
所説ありますが、
その一つを...。
平安時代に在原業平という今でいうイケメンチャラ男?が各地を旅していたところ
このまちに来た時に、
どうも道に迷ってしまったようで、
日も暮れて、雨も降って来てにっちもさっちもいかなくなってしまいました。
しばらく歩いているとようやく、人家を発見。
たずねるとその家は年老いた祖父と娘の二人暮らし。
娘さんは心の優しい人で、
「おもてなしできるといえば、この藁のみです。
でも、藁の火で暖をとりますと、3里(1里約3.92km)を歩いても寒さを感じないほど体の芯から温まります」と
燃料として大事な稲藁をどんどん燃やしてくれました。
「里の名前は?」ときくと名前はまだないとのこと。
どんな辺鄙な場所でも人の住む里に名がないのはおかしいと、
「これからは藁火の里と呼ぶように」といったとのことです。
この娘さんにも素敵な歌作ってあげたんだろうなぁ
女子のワークファッション
当店は作業着やです。^_^
鳶衣料の他に、安全靴、仕事に使う道具など取り揃えております。
ご来店くださるお客様は圧倒的に男性の方が多いです。
また、昼間などは近所でお仕事されてる方の他に、奥様や彼女たちが、頼まれてソケットや手甲など買いに来られます。
建設業はかつて男の職場といわれておりましたが、国の政策や人口の減少などで
いまでは少しずつ女性が活躍する現場も増えてきているようです。
もともとレディースの作業着自体が少ないのもありますが、当店のように小さいお店ですと、男性向けの作業着をどうしてもメインで多く陳列することになります。
そこでHPの方でメンズでも女子が着る事ができる「かっこかわいい」ワークファッションカテゴリー作りました。
彼氏の作業着を借りてもOK,おそろいで着てもOKのワークファッションカテです。
ワークファッションは安全第一が一番の特徴です。ちょっとしたDIYなどをする時も、Tシャツなどの「汚れてもいい格好」から「安全に作業できる服」へ、意識を変えてみてもいいかもしれません。男性も女性も安全に着る事のできるワークファッション、少しずつアップしていきたいと思います。
蕨
11月に入りました。今年もあと2ヶ月、はやいものです。
スタバではすでにクリスマス仕様。
せわしない日常になりがちですが、気持ちだけは冷静に穏やかに、カウントダウンまで予定を立てて過ごしたい物です。(理想(^^*))
さて、1968年に創業いたしました有限会社上田衣料ですが、
今月50周年を迎える事となりました。
本当に本当に感謝申し上げます。
聞いたところによると、開店当時は店の前は田んぼで虫の声で眠れない日もあったとか。
50年経った今、前の道路はアスファルトになり\(^^)/、
ダイソーや吉野家、おかしのまちおかなんでも揃ってます!
おかげさまでそんな待ちの移り変わりを感じながら営業することができました。
これからも、皆様に愛されるお店でいられるよう、精進していきたいと思います。
どうぞこれからも蕨上田をよろしくお願いいたします。
じゅん散歩
じゅん散歩蕨、26日に無事放映されました。
直後にご来店くださった方は、
「ここはしょっちゅう通っているけど、作業着屋さんだなんて気付かなかったよ」と、言って、靴下を買われていきました。
その後もたくさんの方にお声をかけてくださり、反響の大きさを見に染みて感じました。
撮影されるに当たって、
プロデューサー?の方が
何度もお見えになり、
私たちの話、作業衣の話、蕨の話など、
色々聞かれて、
今までに上がってない蕨を出したい、
この番組で蕨に興味を持ってくれる人がいたら嬉しい、と、語られていたのが印象的でした。
時間にして、3分くらいだったと思いますが、
編集をし、
何度も来られては、撮り直しをし、
まして素人ですので、素を出しつつ、
うまくまとめてく事がどんなに大変な事なのか、私でも分かります。
ホントにお疲れ様でしたm(_ _)m。
これだけの情熱をかけて撮って下さった想いに応えられるように、
これからも謙虚に地道に愛されるお店作りを心がけたいと思います。
今度浅草のうちはらみ食べに行ってみますね
(^_−)−☆
寅壱さんのヒストリー
鳶衣料の代表格、といえば「寅壱」。
当店でも、
初期の頃から、
大変お世話になっています。
そんな寅壱さんのヒストリー、
まとめてみました。
1959年村上被服本店設立。
作業服の縫製工場として立ち上げました。
先代の社長さんが
鳶の存在を知ったのは、
出張先の大阪。
以前にも書きましたが、
この頃はまだ鳶のメーカーがなくて、
小売店のミシンで、
職人さんたちのオーダーに個々に別注で作っていたそうです。
この鳶を先代さんが、
試しに買って、
全国の鳶さんに着てもらいたいと、
自らパターンを起こしたのが始まりだそうです。
(その時のパターンはまだ専用倉庫にしまってあるそう。←見たい)
1975年頃から、
カラー展開が始まります。
そう、あの2530シリーズ!
ヒットしすぎてしまったため、
派手な色の服を着た職人さんが増えて、
ゼネコンさんから
赤はダメです。とか言われてしまったそう
1975年から1985年にかけて、
徐々に長くなるという現象を作り出します。
ロング八分(1985年)→
超々ロング(1988年)→
超超超ロング(1990年)。
景気が良くなっていくにつれて、
長くなってきます。
その後、
2008年鳶のカジュアル化がすすみます。
いわゆる「鳶カジ」。
公共事業が減ってきた時期と重なります。
ビームス、セブンイレブン、キティちゃんなどとコラボして、少しずつ裾野を広げていきます。
海外からも、
ダンスウェアやコスプレなどで
注目をあびているそうです。
でも、社長さんは、
「やっぱり鳶服、作業服として、
きてもらいたい」との事。
そして、最近は、
細身やストレッチなどのデニムワークの扱いが増えています。
(今回の新作デニム8940シリーズも売れてますものね)
そう考えると
ずっと同じものを続けて作っていくのって、
簡単なようで難しいのだと思いました。
需要が減れば、
商品にするのも少なめになる。
逆にみんなが欲しいものがあれば、
それを商品にする。
どこかの記事で読みましたが、
100年続いている会社で
アパレルでの100年企業って、
なかったかあまりなかったかって…。
(要確認。)
是非、寅壱さんには、
あと40年ですね!
100年企業目指して頑張って下さい!