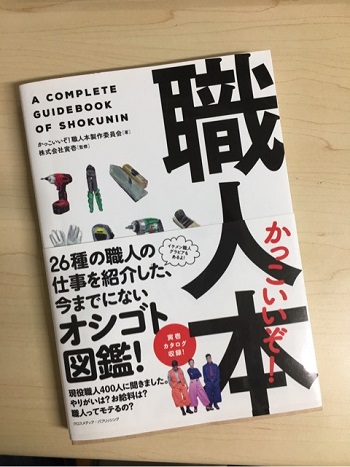新年
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は格別のご愛顧賜りまして厚く御礼申し上げます。
本年もより皆様に喜んでいただけるよう精進する所存でございます。
昨年同様どうぞよろしくお願いいたします。
本年も皆様にとりまして輝かし年でありますよう祈念いたします。
クリスマス
今年も残すところあと1ヶ月となりました。
先日大宮に行きましたら、どこからともなくクリスマスソングが流れてきてウキウキした気分になりました(#^_^#)
だんだんと寒くなってきて、外に出るのもおっくうだなあと身体がしんどくなっていましたが、
一歩外に出ると街はクリスマスの飾り付け、音楽、カフェではコーヒーカップがクリスマス仕様になっていたりとこの時期は町中が私たちを楽しませてくれます。
うれしいことにワム!やマライヤキャリー、山下達郎の我々世代にとっておなじみの曲も健在です!
年越しまであとわずか、2017年を楽しみつつ、ハメを外しすぎず、来る2018年に向けて準備していきたいと思います。
50周年キャンペーンまだ実施中です^ ^。
赤ラベルや市松模様の鳶服、皮手などお買い得商品、
椿モデルのハーネス、タジマの新商品など取り揃えております。
寅壱さんのヒストリー
鳶衣料の代表格、といえば「寅壱」。
当店でも、
初期の頃から、
大変お世話になっています。
そんな寅壱さんのヒストリー、
まとめてみました。
1959年村上被服本店設立。
作業服の縫製工場として立ち上げました。
先代の社長さんが
鳶の存在を知ったのは、
出張先の大阪。
以前にも書きましたが、
この頃はまだ鳶のメーカーがなくて、
小売店のミシンで、
職人さんたちのオーダーに個々に別注で作っていたそうです。
この鳶を先代さんが、
試しに買って、
全国の鳶さんに着てもらいたいと、
自らパターンを起こしたのが始まりだそうです。
(その時のパターンはまだ専用倉庫にしまってあるそう。←見たい)
1975年頃から、
カラー展開が始まります。
そう、あの2530シリーズ!
ヒットしすぎてしまったため、
派手な色の服を着た職人さんが増えて、
ゼネコンさんから
赤はダメです。とか言われてしまったそう
1975年から1985年にかけて、
徐々に長くなるという現象を作り出します。
ロング八分(1985年)→
超々ロング(1988年)→
超超超ロング(1990年)。
景気が良くなっていくにつれて、
長くなってきます。
その後、
2008年鳶のカジュアル化がすすみます。
いわゆる「鳶カジ」。
公共事業が減ってきた時期と重なります。
ビームス、セブンイレブン、キティちゃんなどとコラボして、少しずつ裾野を広げていきます。
海外からも、
ダンスウェアやコスプレなどで
注目をあびているそうです。
でも、社長さんは、
「やっぱり鳶服、作業服として、
きてもらいたい」との事。
そして、最近は、
細身やストレッチなどのデニムワークの扱いが増えています。
(今回の新作デニム8940シリーズも売れてますものね)
そう考えると
ずっと同じものを続けて作っていくのって、
簡単なようで難しいのだと思いました。
需要が減れば、
商品にするのも少なめになる。
逆にみんなが欲しいものがあれば、
それを商品にする。
どこかの記事で読みましたが、
100年続いている会社で
アパレルでの100年企業って、
なかったかあまりなかったかって…。
(要確認。)
是非、寅壱さんには、
あと40年ですね!
100年企業目指して頑張って下さい!
川崎7分
寅壱さん、
寅壱さーん、
ありがとう!。
忙しいのにもかかわらず、
調べていただきました!
鳶衣料が鳶衣料として認知されたのは、
どの辺からなのか…。
ルーツはなんとなく、想像できたのですが、
どこから始まったのか、
ずーっと気になってたんです。
前も書きましたが、町火消しとは形が違うし、
帝国陸軍のズボンとも、繋がらないし…。
そしたら、
寅壱の担当の方が調べて下さったんです
ありがとうございますm(__)m!
寅壱さんによりますと、
諸説ある事はさておき…、
高度成長期ぐらいに、
神奈川の川崎地区らへんで
川﨑7分という名で、
ワタリの広い作業ズボンを仕立てでつくっていたそうなんです!
「川﨑7分で検索したら、
川崎駅から7分。
という記事がなんて多い事!
関連した記事が出てきたのは、
川﨑7分を英訳したものだけでした
(鳶tobiのダブダブのズボンbaggy trousersなんちゃらかんちゃら…)
鳶ってtobiなんだ^ ^。
そう、
「仕立て」だったんです。
職人さん自らおあつらえ、「仕立て」。
当時の鳶職人の方が、
「これでは動きづらいから、
幅の広いの作ってよ。裾はヒラヒラしてると邪魔だから、すぼめてね。」
と、いった感じで、
作ってもらったのが最初なんですね!
感動
そして
スッキリ
東京タワーが初めかどうかは
分かりませんが、
当時、安全帯もせず、
狭い足場で、
作業を続ける方にとって、
仕事=命がけなわけで、
今までの作業服では、
合点がいかなかった。
それで、
あの様な形に
特別に仕立ててもらった。
どういった形だったら、
作業効率が上がるのか、
どういった形だったら、
モチベーションが上がるのか、
実際に現場に出ている方が
生み出した
究極の作業服、
それが鳶衣料!
だったのかな、なんて^ ^。
個人で作られたのか、
チームで作られたのかは分かりませんが、
自分たちが、
当時最も危険な現場で、
動きやすいように、
効率性を考えて
あつらえた鳶衣料が、
今もこうして、
日本を支える職人さんたちが現役として着用してくれている。
想いが繋がっている。
あの時代を作りあげてきた先輩たちが
自分たちで考えた鳶衣料を纏って、
仕立ての職人さんも、
希望に叶う鳶衣料を作って、
みんながそれぞれ真剣に、
自分の役割でもって
仕事に向き合って、
あの時代があったのだと。
「負」もあるかもしれないけど、
モーレツ、じゃないな、
自分の行動がこれからの日本を作るんだ
といったあの時代を想像すると
なんでだろう泣けてくる。
秋
10月突入いたしました。
すっかり秋の気配を感じるようになりました。
皆さんはどんな時に秋を意識しますでしょうか。
●食卓のお皿の上が温かい物に変わったとき
●テレビを消して、静かな雰囲気を味わいたくなった時。
●早く寝てしまうのがもったいないと思った時。
●お休みの日はちょっと遠出したくなった時。
というわけで、土曜日の定休日を利用して
高尾山、行ってまいりました!
紅葉にはまだまだ早かったですが、
山独特の凛とした空気で秋を感じる事ができました。
帰りは10月15日まで行っております高尾山ビアマウンテン!
八王子の夜景を見ながら、飲み放題食べ放題2時間勝負!
外で飲むビールは格別なものですが、私にとりしましてはやはり夏の風物詩という印象です。
さすがにこれはもうギリギリという感じで
夏の名残を惜しみつつ、初秋を味わうというまさに季節の移り変わりを感じる事ができた最高のイベントでした。
今が旬!
ジップアップ入荷しました!
ルーツ
超超ロングってどうしてああいう形をしているのですか?
と、聞かれることがままあります。
ふくらみがあって、下がすぼんでいて…。
まだまだ勉強不足で、わかってないことが多いので、自分なりにまとめてみました。
よくいわれているのが、
①オランダニッカポッカ説。
1800年代当初、欧米でゴルフや自転車、乗馬などのスポーツウエアとして広まりました。
日本では裾が邪魔にならないし、
また、身体の可動域を狭めずに自由自在な動きができると言う事で作業着として用いられたという説。
たくさんの道具を使う現場において、
ズボンの裾が引っかかってしまう可能性も高いですし、
何かにぶつかる(火なども!)時に、
直接肌に到着するまでに時間があるので、
冷静な対応ができる。と、いったこともあるでしょう。
これらは機能性のところで、とても納得する部分でもあります。
あと、もうひとつは
②お公家説。
天皇にお仕えする貴族たちが、
括り袴、指貫という
裾を紐で結んだ袴をはいていました。
生地をふんだんに使った贅沢な衣服だなあという印象です。
神様に近い(昔は)存在の方が召していた服装を
空、天に近い所で仕事をしている鳶の職人さんたちが似たような感じの服装をする。
また、「鳶装束」というくらいだから、
危険が多く、
いつ何時何が起こるかわからない
覚悟のいるお仕事なので、
あの様な天(神)に近い格好をするのではないかと、結びつけたくなりましたが…。
日本の信仰的なところからきているのかなぁと。
違うかなぁ。
鳶というと、
町火消しを想像するのですが、
残っている絵などをみると、
あのふくらんだズボンは履いてないので、
ここからではなさそうです。
そのあと、帝国陸軍の軍服も、7分ズボンのようなものをはいています。
そして、よく目にする
東京タワーを建設している職人の方々たち。
職人さんたちがはきはじめたのは、
この頃が始めなのでは、と、思います。
まとめますと、由来というよりも、
色々な場所、
色々な時代に
それぞれの必要性に応じてこの形が出来上がったのだと思いました。
そしてそして
イメージだけではないのでしょうが、
超超ロングが、禁止されてる箇所が多いと
聞きましたが、
私からみると、
パイロットの制服、
サラリーマンのスーツ、
板前さんの厨房服、
警察官の制服、
自衛隊の服装となんら変わりがないわけで、
普段は、
家族思いのパパだったり、
魚釣りに命をかけてたり、
美術館巡りが趣味だったり、
でも、この服を着たら、
仕事モードになる。
気持ちを切り替える事ができる
この服を着たら、
みんな仕事の顔になる、
仕事をするためにもっともふさわしい制服としての服装なのではないか。
そう思ったりもします。
でも今は普段着のようなカジュアルな作業着が業界を席巻してます。
カッコいいです。。確かにウンウン。
当店もカッコイイ感じの置いてます…。
そして、そんなカッコイイ感じのワーク、
増やしてます。でも…。

地球上のあらゆるところで、
昔から自然発生的にこの形が重宝されたのかな。
3月
3月に入りました。
寒さも和らぎはじめ、
近所の梅の花はもう満開です。
周りの景色が少しずつ色づき始め寒暖を繰り返しながら、
春が近づいてきます。
また、3月といえば卒業、異動のシーズンでもあります。
そして新しい出会いの季節でもあります。
次のステップに向けての準備は整いましたでしょうか。
当店では今月
ヘルメット祭り、皮手祭り開催いたします(#^.^#)!
*ヘルメット型代サービス。
1つからでも承ります。
*皮手5双50円引き。
お好きな皮手どれでも5双で50円引きになります。
この機会にぜひ!
立春
2月に入り節分、立春と暦の上では春が近づいてくるような感じですが、まだまだ冬を実感する寒さが続いています。
今年は例年より気温がやや低いそうなので、防寒グッズがまだまだ活躍しそうです。
どうぞ引き続き体調管理を万全になさってくださいませ。